七五三の参拝では、神社に「初穂料」を納めるのが一般的です。
その際に使う封筒(のし袋)の選び方や書き方には決まりがあり、事前に知っておくと安心です。
特に表書きや中袋の記入方法、お札の入れ方、兄弟での連名ルールなどは、初めて準備する方が戸惑いやすいポイントです。
この記事では、七五三の初穂料を包む封筒について、基本マナーから具体的な書き方、さらにはフルバージョンの記入例までわかりやすく紹介します。
この記事を読めば、当日スムーズに神社へ参拝でき、気持ちよく七五三を迎えられます。
封筒の準備に自信を持って臨めるよう、ぜひ最後までチェックしてみてください。
七五三で神社に納める初穂料とは?
七五三の参拝では、神社に「初穂料(はつほりょう)」を納めるのが一般的です。
この初穂料は、神さまに祈祷をしていただくお礼として渡すものです。
ここでは、初穂料の意味や、よく混同される「玉串料」との違いを解説します。
初穂料の意味と役割
「初穂料」とは、もともとその年に初めて収穫した稲や農作物を神さまに捧げる風習からきた言葉です。
現代ではお米や作物の代わりにお金をお供えする形になり、神社で祈祷を受ける際のお礼として渡します。
七五三の初穂料は、子どもの健やかな成長を感謝し、これからの無事を願うためのお供えと考えるとわかりやすいです。
| 言葉 | 意味 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 初穂料 | 神さまへのお供え(祈祷の謝礼) | 七五三、厄払い、安産祈願など |
| 玉串料 | 神前に玉串を捧げる際のお礼 | 葬儀、地鎮祭、神前結婚式など |
玉串料との違い
「初穂料」と「玉串料」は混同されやすい言葉ですが、使い分けがあります。
七五三の祈祷は「神さまに子どもの成長を祈るお祭り」ですので、一般的には初穂料と書くのが正解です。
ただし、地域や神社によっては「玉串料」と表記するよう案内されることもあります。
その場合は、神社の案内に従うのが一番安心です。
七五三の封筒(のし袋)の選び方
七五三の初穂料を納める際には、どんな封筒を使うかも大切なマナーの一つです。
基本的には「のし袋」を使用しますが、他にもいくつか選択肢があります。
ここでは、封筒選びの基本と注意点を整理してみましょう。
紅白蝶結びの意味と選ぶポイント
七五三の封筒は、紅白の蝶結びの水引がついたのし袋が最も一般的です。
「蝶結び」はほどいて何度でも結び直せる形なので、「成長の節目を何度でも祝えるように」という意味が込められています。
一方で、結婚式などで使う「結び切り」は「繰り返さない」意味があるため、七五三には不向きです。
| 水引の種類 | 意味 | 七五三での可否 |
|---|---|---|
| 紅白蝶結び | 何度でも祝いを重ねられる | ◎(最適) |
| 紅白結び切り | 一度きりのお祝い | ×(不適切) |
| 金銀結び切り | 婚礼や弔事用 | × |
白封筒や簡易封筒は使える?
のし袋が手元にない場合、白い無地の封筒を代用することも可能です。
ただし、七五三は慶事であるため、できる限り華やかで丁寧なのし袋を選ぶのが望ましいです。
神社で受け取る方が見てすぐに「七五三のお祝い」とわかるようにするのが大切なポイントです。
のし袋はどこで買えるのか
のし袋は、文房具店やデパート、スーパー、100円ショップなどで手軽に購入できます。
最近はオンラインショップでも購入でき、デザイン性の高い七五三専用ののし袋も見つかります。
子どもの年齢に合わせた可愛らしい柄のものを選んでも良いですが、基本はシンプルで清らかな印象のものが無難です。
封筒(のし袋)の正しい書き方
七五三の初穂料を包む封筒には、表面に正しい形式で文字を書く必要があります。
ここでは、表書きの書き方、子どもの名前の書き方、そして筆記用具の選び方について解説します。
例文を交えて具体的に見ていきましょう。
表書きの書き方(初穂料・御初穂料)
封筒の表の中央上部には、「初穂料」または「御初穂料」と書きます。
どちらでも正しいですが、「御初穂料」と書くほうが丁寧な印象になります。
ただし、「御初穂料」は4文字のため、縁起を気にしてあえて「初穂料」とする地域もあります。
【例文:表書き】
| 書く場所 | 記入例 |
|---|---|
| 中央上段 | 御初穂料 |
| 中央下段 | 山田 太郎 |
子どもの名前の書き方と連名ルール
水引の下には、祈祷を受ける子どものフルネームを書きます。
兄弟姉妹で一緒に祈祷を受ける場合は連名で書くのが基本です。
その際は、年齢の高い子を右から順に書きます。
【例文:兄弟の場合】
| 記入例 |
|---|
| 山田 太郎 山田 花子 |
毛筆・筆ペンを使うべき理由
表書きは、できる限り毛筆または筆ペンで書きます。
ボールペンやサインペンは線が細く、慶事にはふさわしくありません。
毛筆や筆ペンで書いた文字は太く濃く、祝いの気持ちをより丁寧に表すことができます。
文字の美しさよりも、心を込めて丁寧に書くことが大切です。
中袋の書き方と記入例
のし袋には中袋がついていることが多く、ここにも正しく書くべき内容があります。
特に金額や住所、名前の書き方には決まりがあるため、具体例を交えて確認していきましょう。
金額を大字で書く理由と書き方例
中袋の表面には金額を書きます。
金額は漢数字を崩した「大字(だいじ)」で書くのが一般的です。
大字は数字の改ざんを防ぐために使われる書き方です。
【大字の例】
| 金額 | 大字での書き方 |
|---|---|
| 5,000円 | 金伍阡円 |
| 10,000円 | 金壱萬円 |
| 30,000円 | 金参萬円 |
【例文:中袋表面】
金壱萬円
住所と名前の正しい書き方
中袋の裏面には住所と名前を書きます。
これは神社が祈祷を受ける人を確認するためのものです。
子どもの名前を書くのが基本ですが、必要に応じて保護者の名前を添える場合もあります。
【例文:中袋裏面】
| 〒123-4567 |
| 東京都千代田区丸の内1-1-1 |
| 山田 太郎 |
フルバージョン完成例
ここで、中袋の表・裏をまとめた完成形の例文を紹介します。
【中袋完成例】
| 面 | 記入内容 |
|---|---|
| 表面 | 金壱萬円 |
| 裏面 | 〒123-4567 東京都千代田区丸の内1-1-1 山田 太郎 |
中袋は神社にとって大切な確認資料になるため、丁寧に記入することがマナーです。
お札の入れ方と封筒の折り方
お札の入れ方や封筒の折り方にも、七五三ならではのマナーがあります。
せっかく丁寧に書いたのし袋も、中身の入れ方が間違っていると印象を損ねてしまいます。
ここでは、お札の扱い方と封筒の折り方を具体例とともに確認していきましょう。
新札と旧札の扱い方
七五三の初穂料には、できるだけ新札を用意するのが望ましいです。
新札が用意できない場合は、なるべく折れ目や汚れの少ないきれいなお札を選びましょう。
お祝いごとなので「事前に準備していた」という気持ちを表す意味でも新札が最適です。
封筒に入れる向きと折り方の注意点
お札を入れるときは、肖像画が表側にくるように上向きで入れます。
封筒の表とお札の表面の向きを揃えることが大切です。
また、折り曲げずにそのまま入れるのが基本です。
【例文:お札の向き】
| 封筒の向き | お札の入れ方 |
|---|---|
| 封筒の表側 | お札の表(肖像画)が上を向く |
のし袋を閉じる際は、上側の折りを先に下へ折り、その上に下側を重ねます。
これは「慶事は上から下へ流れるように」という考え方に基づいています。
逆にすると弔事の意味になってしまうため注意しましょう。
フルバージョン完成例
実際の入れ方と折り方をまとめると、以下のようになります。
| ステップ | やること |
|---|---|
| ① | 新札を用意する |
| ② | お札の肖像画を上にして封筒の表に合わせる |
| ③ | 折らずにそのまま中袋へ入れる |
| ④ | 外袋を閉じるときは上側を先に折り、下側を上に重ねる |
神社での初穂料の渡し方
七五三当日、神社に持参した初穂料をどうやって渡すかも知っておきたいポイントです。
ここでは、袱紗(ふくさ)の使い方や受付での渡し方、渡すタイミングを解説します。
しっかり準備しておくと、当日に慌てず安心です。
袱紗に包むマナー
初穂料は、そのままバッグに入れるのではなく袱紗(ふくさ)に包んで持参します。
袱紗はご祝儀や大切な金品を清浄に保ち、相手に敬意を示すための布です。
七五三では紫やえんじ色など落ち着いた色合いを選ぶと安心です。
| 袱紗の色 | 一般的な使い分け |
|---|---|
| 紫 | 慶事・弔事どちらにも使える万能色 |
| えんじ色 | 慶事向け(女の子の七五三に多い) |
| 藍色 | 慶事向け(男の子の七五三に多い) |
受付での渡し方と挨拶の仕方
神社に着いたら、祈祷の受付で初穂料を渡します。
袱紗から封筒を取り出し、相手側(受付の方)に表書きが向くようにして両手で差し出します。
その際は、「よろしくお願いします」と一言添えると丁寧です。
【例文:受付での言葉】
- 「七五三の祈祷をお願いいたします。本日はどうぞよろしくお願いします。」
- 「こちら、初穂料です。よろしくお願いいたします。」
渡すタイミングと流れ
初穂料を渡すタイミングは、祈祷を申し込むときが一般的です。
事前に予約をしている場合は、受付で「予約している〇〇です」と伝えたうえで渡しましょう。
神社によっては祈祷後に納める場合もあるため、案内があれば必ず従います。
【渡し方の流れ】
| ステップ | やること |
|---|---|
| ① | 受付に並ぶ前に袱紗を準備する |
| ② | 自分の番になったら袱紗から封筒を取り出す |
| ③ | 表書きが相手に向くように両手で渡す |
| ④ | 「よろしくお願いします」と一言添える |
七五三の初穂料の金額相場
七五三で神社に納める初穂料には、おおよその相場があります。
ただし、金額は地域や神社ごとに異なるため、事前に確認しておくと安心です。
ここでは一般的な金額の目安と、有名神社の例、兄弟姉妹の場合の注意点を紹介します。
一般的な金額目安(5千円~1万円)
七五三の初穂料は1人あたり5,000円〜10,000円が一般的です。
祈祷の内容や記念品の有無によって金額が変わる場合があります。
5,000円:シンプルな祈祷のみ / 10,000円:祈祷+記念品ありとイメージするとわかりやすいです。
有名神社の相場一覧
神社によっては、公式サイトに金額が掲載されていることもあります。
目安として、代表的な神社の例を紹介します。
| 神社名 | 初穂料 |
|---|---|
| 明治神宮(東京) | 5,000円・10,000円・30,000円 |
| 鶴岡八幡宮(神奈川) | 10,000円 |
| 春日大社(奈良) | 5,000円(小祈祷)〜30,000円(大祈祷) |
| 住吉大社(大阪) | 10,000円 |
| 太宰府天満宮(福岡) | 6,000円 |
兄弟・姉妹で納める場合の注意点
兄弟姉妹で一緒に祈祷を受ける場合は、人数分をまとめて包むのが基本です。
例えば、1人10,000円の場合、2人なら20,000円を1つの封筒にまとめます。
ただし、神社によっては「きょうだい割引」がある場合もあります。
事前に確認しておくと、準備がスムーズです。
【例文:兄弟2人で納める場合の中袋表記】
金弐萬円
七五三の封筒マナーでよくある質問
七五三の初穂料を準備するときに、細かい点で迷うこともあります。
ここでは、特によくある質問をまとめ、例文を交えて解説します。
知っておくと安心できるポイントばかりなので、参考にしてください。
ボールペンで書いても良い?
封筒に名前や金額を書く際、ボールペンは避けるのが基本です。
線が細く見栄えが弱いため、慶事には向きません。
毛筆や筆ペンを使うと、力強く丁寧な印象になります。
連名に親の名前は必要?
七五三は子どもの成長を祝う行事なので、封筒には子どもの名前を書きます。
兄弟姉妹がいる場合は連名で書き、年齢の高い子を右から順に並べます。
親の名前を添えるかどうかは地域や神社によりますが、案内があれば従いましょう。
【例文:兄弟連名+親を添える場合】
| 山田 太郎 山田 花子(山田 健一・麻衣) |
新札が用意できないときは?
新札を使うのが理想ですが、どうしても用意できない場合は折り目や汚れの少ないお札を選びましょう。
なるべくきれいなお札を選ぶことで、気持ちを丁寧に伝えることができます。
複数の小額紙幣を合わせるより、1枚でまとめる方がスマートです。
フルバージョン完成例(外袋・中袋)
最後に、七五三の初穂料封筒を一通り完成させた例を紹介します。
| 場所 | 記入例 |
|---|---|
| 外袋(表書き上) | 御初穂料 |
| 外袋(表書き下) | 山田 太郎 |
| 中袋(表) | 金壱萬円 |
| 中袋(裏) | 〒123-4567 東京都千代田区丸の内1-1-1 山田 太郎 |
この完成例を参考にすれば、当日も迷わず準備ができます。
まとめ|七五三の封筒の書き方を押さえて安心して参拝しよう
七五三の初穂料は、神さまへの感謝と子どもの成長を願う気持ちを形にしたものです。
そのため、封筒選びや書き方にも丁寧さが求められます。
この記事で紹介したマナーを押さえておけば、当日も自信を持って神社に参拝できます。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 封筒の種類 | 紅白蝶結びののし袋を使う |
| 表書き | 「初穂料」または「御初穂料」と書く |
| 名前 | 子どものフルネームを書く(兄弟は連名) |
| 中袋(表) | 金額を大字で書く(例:金壱萬円) |
| 中袋(裏) | 住所と名前を書く |
| お札 | 新札を用意し、肖像画を上向きにして入れる |
| 渡し方 | 袱紗に包み、受付で「よろしくお願いします」と渡す |
七五三は家族にとって大切な節目の行事です。
封筒の準備を丁寧に整えることで、より心のこもった参拝ができ、素敵な思い出につながります。
ぜひ本記事を参考にして、安心して七五三を迎えてください。

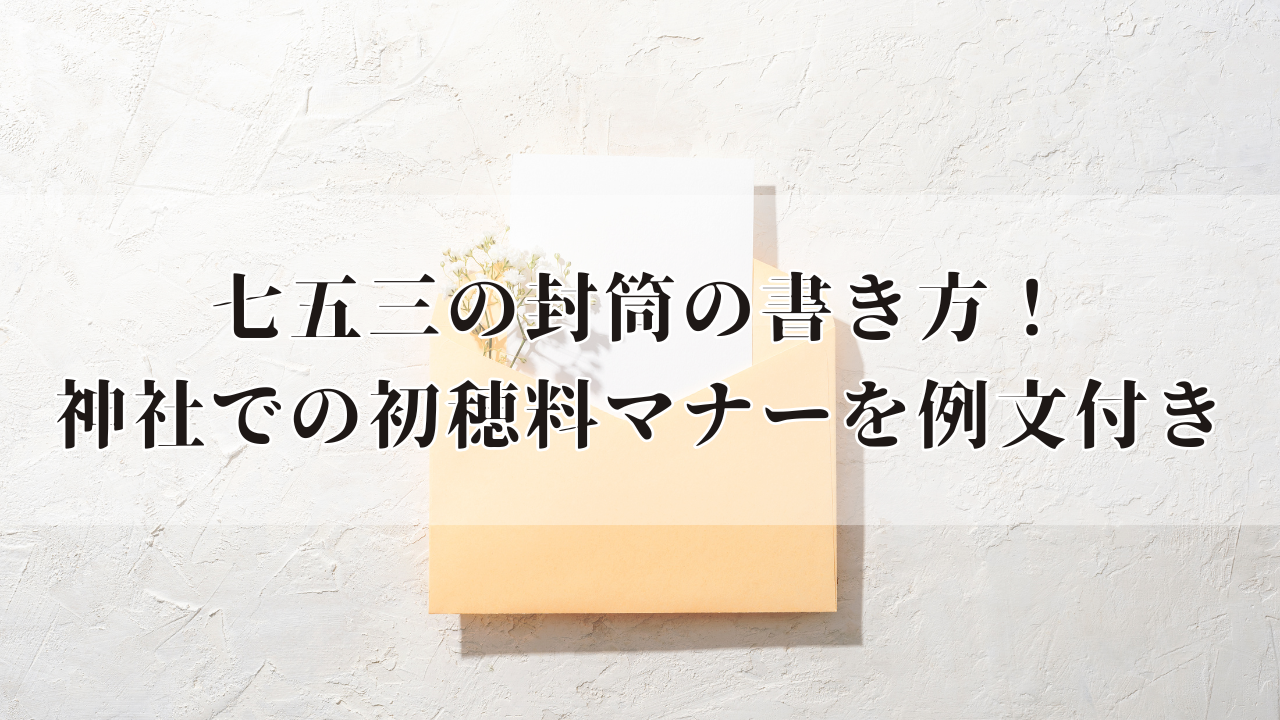
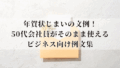
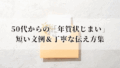
コメント