七五三は、子どもの健やかな成長を願う日本ならではの大切な行事です。
神社でのご祈祷をお願いする際には「初穂料(はつほりょう)」と呼ばれるお金を納めますが、金額はいくらが相場なのか、のし袋はどんなものを選べばよいのか、さらには書き方や渡し方のマナーなど、迷うポイントが多いですよね。
この記事では、七五三の初穂料についての基礎知識から、金額相場、のし袋の選び方・正しい書き方、そして神社での渡し方までをわかりやすくまとめました。
初めて七五三を迎えるご家庭でも、これを読めば安心して準備が整えられるはずです。
正しいマナーを知ることで、七五三という特別な一日を心穏やかに迎えられます。
ぜひこの記事を参考に、お子さまの大切な節目をしっかり準備してあげてください。
七五三で神社に納める「初穂料」とは?
七五三の参拝で神社に納めるお金のことを「初穂料(はつほりょう)」と呼びます。
これは単なる料金ではなく、子どもの成長を神様に感謝し、祈願を込めてお供えする大切なお金です。
ここでは、初穂料の意味や「玉串料」との違いを分かりやすく解説します。
初穂料の意味と由来
「初穂」とは、その年に初めて収穫された稲や農作物のことを指します。
古来、日本では収穫したての作物を神様に奉納し、豊作や家族の健康を祈ってきました。
この習慣が時代とともに変化し、作物の代わりに金銭をお供えする形となったのが「初穂料」です。
つまり初穂料は、祈祷をしていただいたことへの感謝の気持ちを神様に届ける手段というわけです。
| 用語 | 意味 | 使われる場面 |
|---|---|---|
| 初穂料 | 収穫物の代わりに神様へ納めるお金 | 七五三、お宮参り、厄払いなど |
| 玉串料 | 玉串(榊の枝に紙垂をつけたもの)の代わりに納めるお金 | 地鎮祭、結婚式、葬儀など |
初穂料と玉串料の違い
神社での祈祷料としてよく耳にするのが「初穂料」と「玉串料」です。
どちらも神様に対する謝礼金を意味しますが、七五三の場合は「初穂料」と書くのが一般的です。
一方で、地鎮祭や結婚式、さらには葬儀などでは「玉串料」と書かれるケースが多いです。
つまり同じように神様へ捧げるお金でも、行事の内容によって表現が変わると覚えておくと安心ですね。
七五三の初穂料はいくら用意すればいい?
七五三で最も気になるポイントのひとつが「初穂料はいくら包めばいいの?」という金額の目安です。
神社によって金額設定が異なるため一概には言えませんが、一般的な相場が存在します。
ここでは、相場の目安や兄弟姉妹で参拝する場合の考え方、さらに地域や神社による違いを整理します。
一般的な金額相場(5,000円〜10,000円)
七五三の初穂料の金額は5,000円から10,000円程度が一般的な相場です。
地域の小規模な神社では5,000円、大規模で有名な神社では10,000円程度が多いとされています。
また、金額が複数コースに分かれていて、お札や記念品の内容によって差がある場合もあります。
| 神社の規模 | 相場の金額 | 特徴 |
|---|---|---|
| 小規模な地域神社 | 5,000円 | 基本的な祈祷のみ |
| 大規模・有名神社 | 5,000円〜10,000円 | 記念品やお札のサイズが異なる |
| 特別祈祷や上位コース | 10,000円以上 | 祈祷内容は同じで記念品の違い |
兄弟・姉妹で参拝する場合の考え方
兄弟や姉妹で同時に祈祷を受ける場合は、基本的に「人数分の初穂料を用意する」のが原則です。
例えば、子ども2人なら5,000円×2=10,000円、3人なら15,000円という計算になります。
ただし、神社によっては2人目以降は割引が設定されている場合もあるため、事前に確認するのがおすすめです。
地域や神社ごとの違いと調べ方
初穂料の金額は地域や神社によって異なります。
特に有名な神社では、公式サイトに「七五三祈祷料」として金額が明記されていることが多いです。
一方で「お気持ちで」と案内される神社もあり、この場合は5,000円を目安にすると安心です。
調べ方としては以下の方法があります。
- 神社の公式ホームページで確認する
- 直接電話で問い合わせる
- 口コミや体験談を参考にする
わからないまま当日を迎えると不安になりますので、必ず事前に確認することが大切です。
七五三のお金を入れる「のし袋」の選び方
初穂料を神社に納める際は、そのまま現金を渡すのではなく「のし袋」に入れるのが一般的なマナーです。
しかし、のし袋には種類が多く、どれを選べばいいのか迷ってしまう方も多いですよね。
ここでは、七五三にふさわしいのし袋の種類や、代用できるケース、さらに持参時のマナーを紹介します。
蝶結びが選ばれる理由
七五三の初穂料には、紅白の蝶結び(水引が何度でも結び直せる形)ののし袋を使います。
蝶結びは「何度あっても喜ばしいこと」に使われるため、子どもの成長を祝う七五三にぴったりです。
逆に、結婚式で使う「結び切り」は一度きりの意味を持つため、七五三では使用しないよう注意してください。
| のし袋の種類 | 用途 | 七五三での可否 |
|---|---|---|
| 蝶結び(花結び) | 出産祝い、入学祝い、七五三など | ◎ 適している |
| 結び切り | 結婚式、弔事 | × 適さない |
| あわび結び | 長寿祝い、地域によっては結婚式 | △ 関西では使われる場合あり |
白封筒でもよいケースとは?
神社によっては「白封筒でも構いません」と案内される場合があります。
その場合は郵便番号欄や柄のない真っ白な封筒を使用しましょう。
印刷された紅白水引ののし袋でも問題ありませんが、正式感を出すなら実物の水引が付いたものがおすすめです。
ふくさの使い方と持参マナー
のし袋はバッグにそのまま入れず、必ず「ふくさ」に包んで持参するのがマナーです。
受付ではふくさから取り出して、のし袋を両手で差し出すと丁寧な印象になります。
ふくさは紫色が慶弔どちらにも使えるため、1枚持っておくと便利ですよ。
七五三ののし袋の正しい書き方
のし袋は「どの種類を選ぶか」だけでなく、書き方にも決まりがあります。
表書きや中袋に正しく記入することで、神様への敬意やお子さんへの想いがしっかりと伝わります。
ここでは、七五三にふさわしいのし袋の書き方をわかりやすくまとめました。
表書きに書く言葉と子どもの名前
のし袋の表面、水引の上部には「初穂料」または「御初穂料」と書きます。
水引の下段には、七五三を迎えるお子さんのフルネームを記入します。
兄弟姉妹で一緒にご祈祷を受ける場合は、年齢の高い順に右から並べて連名で書きましょう。
書く際は筆ペンを用いるのが望ましく、ボールペンは避けてください。
中袋に書く金額と住所の書き方
中袋がある場合は、表の中央に金額、裏面に住所と氏名を記入します。
金額は「金 ○○円」と書き、より丁寧にしたい場合は大字(旧漢数字)を用います。
| 金額 | 書き方例(大字) |
|---|---|
| 5,000円 | 金 伍阡圓 |
| 10,000円 | 金 壱萬圓 |
裏面には郵便番号・住所・氏名を記載します。
印刷済みの枠がある場合は、それに従って記入すれば問題ありません。
大字(旧漢数字)の使い方と例
七五三の初穂料では、数字をそのまま書くのではなく、大字で表記するのがマナーとされています。
これは、数字を改ざんされないための工夫であり、古くから伝わる習慣です。
- 一 → 壱
- 二 → 弐
- 三 → 参
- 五 → 伍
- 万 → 萬
「円」を「圓」と旧字体にすると、より格式が高い印象になります。
もちろん通常の漢数字で書いても失礼にはあたりませんが、丁寧さを大切にしたい方は大字を使うと安心です。
お札の入れ方と包み方のマナー
のし袋に入れるお金は「ただ包めばいい」というものではなく、入れ方やお札の向きにも細やかなマナーがあります。
せっかくのお祝い事なので、丁寧に準備して気持ちよく神社に納めたいですよね。
ここでは、新札を用意する理由やお札の入れ方、もし間違えてしまった時の対処法を解説します。
新札を用意する理由
初穂料に入れるお金は必ず新札を用意しましょう。
新札は「これからの新しい人生を祝う」という意味を込めることができ、神様に捧げるのにふさわしいとされています。
銀行の窓口で「新札に両替してください」とお願いすれば用意してもらえます。
郵便局では基本的に両替ができないので注意してください。
お札の向きと折り方
お札を中袋に入れる際には、肖像画が上向きになるように入れます。
さらに表面(人物の顔側)がのし袋の表側と一致するようにしましょう。
これが正式なマナーであり、受付で袋を開けたときに美しく見える工夫でもあります。
| ポイント | 正しい入れ方 |
|---|---|
| 向き | 肖像画を上にして中袋へ |
| 表裏 | 肖像画がのし袋の表面側を向く |
| 折り目 | シワや折れ目のない状態で準備 |
間違えた場合の対処法
もしお札の向きを間違えたり、のし袋に誤字を書いてしまった場合はどうすればよいでしょうか。
基本的には必ず新しい袋に書き直すのがマナーです。
書き損じたのし袋を修正して使うのは避けましょう。
また、どうしても新札を用意できなかった場合は、できるだけ綺麗で折り目のないお札を選び、アイロンを当ててシワを伸ばすといった工夫も有効です。
初穂料を渡すタイミングと神社での流れ
七五三当日、神社に行ったら「初穂料はいつ渡せばいいの?」と戸惑う方も多いでしょう。
ここでは、神社での一般的な流れと、受付での渡し方のマナーを整理します。
当日の行動をイメージしておくと安心して七五三を迎えられますよ。
受付での渡し方
初穂料は祈祷の申し込みをする際に受付へ渡すのが基本です。
社務所や授与所と呼ばれる窓口で申込書を記入し、のし袋に入れた初穂料を手渡します。
直接現金を渡す神社もありますが、事前に準備したのし袋で差し出すのが丁寧です。
| 場面 | 対応方法 |
|---|---|
| 祈祷の申し込み時 | 申込書と一緒にのし袋を渡す |
| 受付カウンターあり | 職員に「初穂料です」と伝えて渡す |
| 事前予約の場合 | 受付で「予約しています」と伝えてから渡す |
言葉の添え方で印象を良くするコツ
初穂料を渡す際には、ただ黙って差し出すのではなく、ひと言添えると印象が良くなります。
例えば、「本日はよろしくお願いいたします」と言葉を添えるだけで十分です。
子どもと一緒に元気に挨拶するのも良い思い出になりますよ。
予約制の神社の場合の注意点
人気の神社や混雑する時期(特に11月)は予約制になっていることがあります。
予約をしている場合は、受付で「予約しています」と伝えることでスムーズに進みます。
また、時間指定がある場合は遅刻しないように注意しましょう。
当日は混雑して待ち時間が長引くこともあるため、子どもの機嫌対策として絵本やお菓子を用意しておくと安心です。
七五三の初穂料でよくある失敗と注意点
七五三の準備では衣装や写真に気を取られ、初穂料の用意が後回しになることもあります。
しかし、細かなマナーを誤ると恥ずかしい思いをすることも。
ここでは、よくある失敗例と注意すべきポイントを整理しました。
金額や名前の書き間違い
のし袋に誤字を書いてしまうのはNGです。
一度書き間違えた場合は修正せず、新しいのし袋に書き直すのがマナーです。
また、金額欄には「金」と必ず付けて記載しましょう。
のし袋の種類を間違えるケース
七五三は何度でも祝える行事なので、のし袋は蝶結びを選ぶのが基本です。
結び切りや弔事用の水引を間違えて選んでしまうと、不適切に見えてしまいます。
コンビニや100円ショップで購入する場合でも、必ず水引の種類を確認しましょう。
| 水引の種類 | 意味 | 七五三での使用 |
|---|---|---|
| 蝶結び | 何度あっても良い祝い事 | ◎ 使用する |
| 結び切り | 一度きりの祝い事、弔事 | × 使用しない |
当日慌てないための準備リスト
七五三当日は子どもの支度や移動でバタバタしがちです。
前日までに以下を準備しておくと安心です。
- 新札を銀行で用意する
- のし袋に「初穂料」と子どもの名前を記入
- 金額を大字で正しく記入
- ふくさに包んでバッグへ入れておく
こうした準備を整えておけば、当日は焦らず落ち着いて神社に向かえます。
何よりも気持ちを込めて用意することが一番大切です。
まとめ|七五三のお金のマナーを押さえて安心の一日に
七五三は子どもの成長を祝う大切な節目であり、神様への感謝を表す場でもあります。
そのため、初穂料の準備やのし袋の書き方、渡し方のマナーを押さえておくことが安心につながります。
ここまでのポイントを整理して振り返りましょう。
初穂料の金額・書き方・渡し方の要点
- 金額相場は5,000円〜10,000円が一般的
- のし袋は紅白蝶結びを使用
- 表書きは「初穂料」または「御初穂料」、下段に子どものフルネーム
- 中袋には大字(壱・弐・伍など)で金額を書くと丁寧
- お札は新札を肖像画が上向きになるように入れる
- ふくさに包んで受付で渡すのが正式な流れ
事前準備で心穏やかに七五三を迎えよう
当日は衣装や写真撮影で忙しくなるため、初穂料の準備は必ず前日までに整えておくのがおすすめです。
新札・のし袋・ふくさをそろえ、名前や金額を間違いなく記入しておけば、当日も焦らずに済みます。
準備が整えば、あとは子どもの笑顔を見守りながら、七五三という特別な時間を心から楽しめます。
マナーを押さえることは「心を込めて祝うこと」そのものです。
ぜひ丁寧な準備で、素敵な一日を迎えてくださいね。

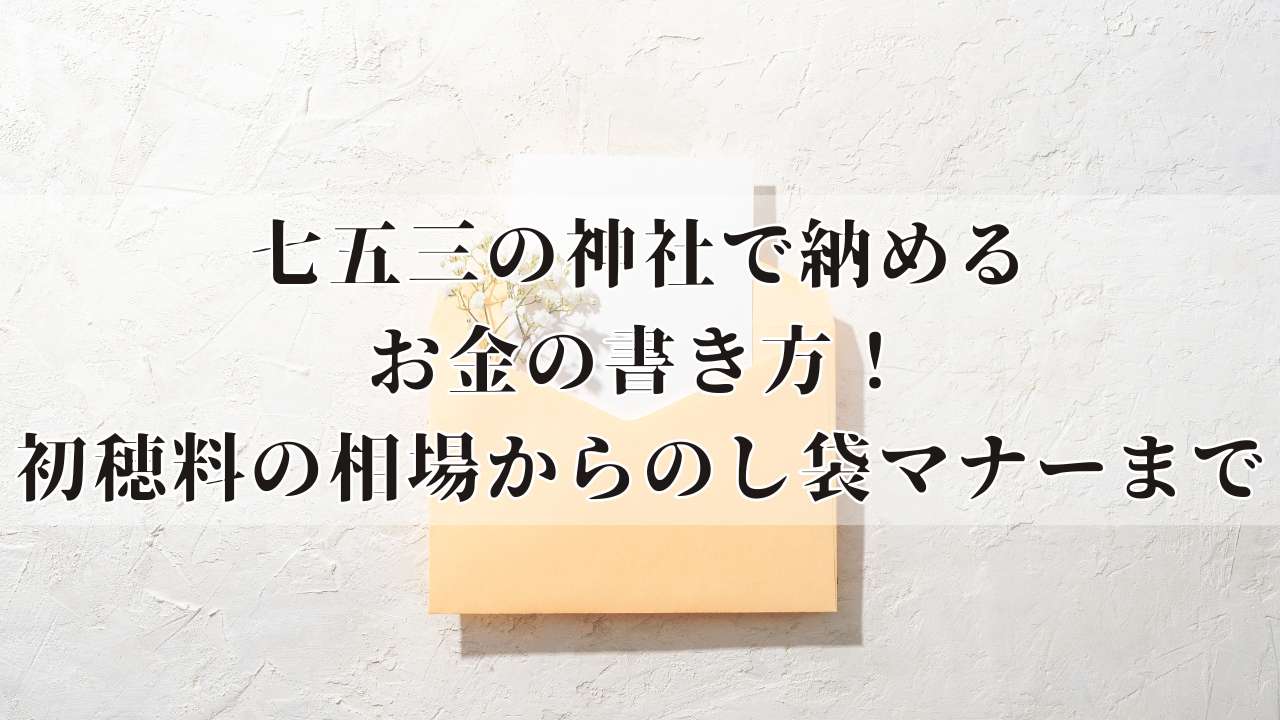
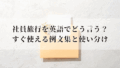
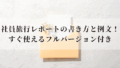
コメント