年が明けると「新年の挨拶」を交わすのが習慣ですが、喪中のときは特別な配慮が必要です。
特に近年は年賀状よりもLINEで新年の挨拶を交わす人が増えており、どう表現すればよいか悩む方も多いのではないでしょうか。
喪中の際は「おめでとうございます」といった祝賀の言葉を控えつつ、相手への感謝や丁寧な気遣いを伝えるのが基本です。
本記事では、LINEで喪中挨拶を送るときのマナーや注意点をわかりやすく整理しました。
さらに「自分が喪中の場合」「相手が喪中の場合」「ビジネスでのやり取り」など、シーンごとに使える例文を多数紹介しています。
そのまま使える短文からフルバージョンの丁寧な文例まで揃えていますので、状況に合わせてアレンジすることができます。
喪中でも心を込めた挨拶をスマートに伝えたい方は、ぜひ参考にしてください。
喪中に新年の挨拶をLINEでするときの基本マナー
ここでは、喪中のときにLINEで新年の挨拶をする際に押さえておきたい基本的な考え方をまとめます。
相手に配慮しながらも失礼のない表現を選ぶことが大切です。
喪中とはどういう期間なのか
喪中とは、近しい家族を亡くしたあとに一定の期間、祝い事を控える慣習のことを指します。
この期間は一般的に一年とされますが、家庭や地域によって違いがあります。
大切なのは「心を落ち着け、祝いを控える気持ちを持つこと」です。
| 喪中の目安 | 意味合い |
|---|---|
| 約1年間 | 近親者を亡くしたあと、祝い事を避ける慣習 |
| 地域や家庭によって異なる | 故人や遺族の思いを尊重 |
なぜ「おめでとう」を避ける必要があるのか
お正月の挨拶は「新しい年を祝いましょう」という意味合いを持ちます。
そのため喪中の場合、通常の「おめでとうございます」という言葉は控えるのがマナーです。
間違って「おめでとう」と伝えてしまうと、相手を戸惑わせてしまう可能性があります。
代わりに「新しい年を迎えましたね」「今年もよろしくお願いします」といったニュートラルな言葉に置き換えるのが良いでしょう。
| 避ける言葉 | 使える言葉 |
|---|---|
| 新年あけましておめでとうございます | 新しい年を迎えましたね |
| 明るい一年になりますように | 本年もどうぞよろしくお願いいたします |
LINEだからこそ気をつけたい点
LINEは手軽で親しみやすい反面、文章が軽い印象になりやすいです。
普段のトークで使うような絵文字や派手なスタンプは、喪中の挨拶にはふさわしくありません。
落ち着いた文面で、短くても丁寧にまとめることを意識しましょう。
| 控えるべき表現 | 望ましい表現 |
|---|---|
| 派手なスタンプや絵文字 | シンプルなテキストのみ |
| フランクすぎる挨拶 | 丁寧な言葉づかい |
自分が喪中の場合のLINE挨拶例文
ここでは、自分が喪中の立場にあるときにLINEで送れる挨拶文を紹介します。
感謝の気持ちと「新年のご挨拶を控える」旨を伝えるのが基本です。
親しい友人・家族への例文
親しい間柄では、堅苦しすぎずに自分の状況を素直に伝えることが大切です。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| カジュアルに伝えたいとき | 「新しい年を迎えましたね。今年もよろしくお願いします。昨年◯月に身内に不幸があり、年始の挨拶は控えさせてもらっています。」 |
| 丁寧に伝えたいとき | 「旧年中は大変お世話になりました。本年もよろしくお願いします。なお、昨年近親者を亡くしたため、新年のご挨拶は控えさせていただきます。」 |
職場や仕事関係への例文
仕事関係では簡潔かつ礼儀正しい表現を心がけましょう。
ビジネスでは「感謝」と「ご挨拶を控える旨」を端的に伝えるのが基本です。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| 上司や取引先に送る場合 | 「昨年は格別のご厚情を賜り、誠にありがとうございました。本年もよろしくお願い申し上げます。なお、私事ですが昨年◯月に近親者を亡くしましたため、新年のご挨拶は控えさせていただきます。」 |
| 職場仲間へ送る場合 | 「昨年はお世話になりました。本年もどうぞよろしくお願いします。身内に不幸がありましたので、新年の挨拶は控えさせていただきます。」 |
短文で伝えるシンプルな例文
LINEでは長文を避け、シンプルに伝える方が自然な場合もあります。
ポイントは「挨拶を控える」ことを一言入れることです。
| 短文例文 |
|---|
| 「新しい年を迎えました。本年もよろしくお願いします。なお、喪中につき新年のご挨拶は控えさせていただきます。」 |
| 「旧年中はありがとうございました。今年もよろしくお願いいたします。喪中につきご挨拶は控えさせていただきます。」 |
また、より丁寧に伝えたいときは以下のようなフルバージョンも使えます。
「昨年は公私ともに大変お世話になり、誠にありがとうございました。本年も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。なお、私事で恐縮ですが、昨年◯月に近親者を亡くしましたため、新年のご挨拶は控えさせていただきます。どうか本年もよろしくお願い申し上げます。」
相手が喪中の場合のLINE挨拶例文
ここでは、相手が喪中のときにLINEで挨拶を送る場合の文例を紹介します。
無理に慰めるよりも、静かな気遣いを表す言葉が大切です。
プライベートな関係での例文
友人や親しい人へのLINEでは、シンプルで優しい言葉を選びましょう。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| 控えめに挨拶する場合 | 「新しい年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願いします。昨年はご家族にご不幸があったとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。」 |
| さりげなく気遣う場合 | 「年頭のご挨拶を申し上げます。昨年は大変な一年であったかと存じます。どうかご無理のないようにお過ごしください。」 |
ビジネス関係での例文
仕事の関係では、フォーマルさを保ちながらも相手の状況に配慮する必要があります。
「祝いを控える表現」と「今後もよろしくお願いします」という二点を組み合わせると安心です。
| 状況 | 例文 |
|---|---|
| 取引先や上司へ | 「年頭にあたりご挨拶を申し上げます。御社にとって本年が穏やかな一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。なお、ご家族にご不幸があったことと伺っておりますので、新年の祝いの言葉は控えさせていただきます。」 |
| 職場仲間へ | 「新しい年を迎えました。本年もどうぞよろしくお願いいたします。昨年はご家族にご不幸があったと伺っております。ご心中お察し申し上げます。」 |
相手に寄り添う気遣いの言葉
喪中の相手にとって、過剰な明るさや形式ばった言葉は重く感じられることがあります。
短くても誠実な気持ちが伝わる言葉を選ぶことが大切です。
| 気遣いを込めた短文例 |
|---|
| 「昨年のご不幸に際し、心よりお悔やみ申し上げます。本年もどうぞよろしくお願いいたします。」 |
| 「ご家族にご不幸があったと伺っております。寒い時期ですので、どうかご自愛くださいませ。」 |
より丁寧に伝えたい場合のフルバージョン例文は以下の通りです。
「年頭にあたりご挨拶を申し上げます。昨年はご家族にご不幸があったとのこと、心よりお悔やみ申し上げます。本来であれば新年を祝う言葉をお伝えすべきところですが、喪中と伺っておりますので控えさせていただきます。本年も変わらぬお付き合いを賜りますようお願い申し上げます。」
LINEでの喪中挨拶に関する注意点
ここでは、喪中の挨拶をLINEで行う際に気をつけたいポイントをまとめます。
ちょっとした配慮の有無で、相手に与える印象は大きく変わります。
避けるべき言葉や表現
喪中のときに一番気をつけたいのは言葉選びです。
特に「おめでとうございます」などの祝いの言葉は避ける必要があります。
何気ない一言が相手を驚かせてしまうこともあるため注意しましょう。
| 避ける言葉 | 代わりの表現 |
|---|---|
| 新年あけましておめでとうございます | 新しい年を迎えましたね |
| 明るい一年になりますように | 本年もどうぞよろしくお願いいたします |
スタンプや絵文字の扱い方
普段のLINEではスタンプや絵文字が便利ですが、喪中の挨拶には不向きです。
派手な色やポップな絵柄は場にそぐわないため避けるのが無難です。
どうしても使いたい場合は落ち着いたデザインのスタンプに限定するのが安心です。
| 避けたいスタンプ | 使ってもよいスタンプ |
|---|---|
| キャラクターがはしゃぐイラスト | シンプルな文字だけのスタンプ |
| カラフルで派手な絵文字 | 無地のシンプルマーク |
送るタイミングの選び方
喪中の挨拶は「元旦の朝に送るべき」という決まりはありません。
むしろ、落ち着いた時期に送るほうが相手の心に寄り添う場合もあります。
三が日を避け、数日後に送るという選択もひとつの配慮です。
| タイミング | 特徴 |
|---|---|
| 元旦の朝 | 形式的に済ませたい場合 |
| 三が日後 | 落ち着いてから送れるため丁寧 |
2025年の最新トレンドと挨拶の変化
ここでは、2025年現在の喪中挨拶に関する最新の傾向やトレンドを紹介します。
年賀状からデジタル挨拶への移行が進む中で、LINEでのマナーにも変化が生まれています。
年賀状からLINEへの移行
近年、年賀状のやり取りは減少し、代わりにLINEやメールでの挨拶が一般的になっています。
特に20〜40代を中心に「年賀状は出さずにLINEで済ませる」というスタイルが定着しています。
喪中の挨拶も同じくLINEで行うのが自然な流れになってきています。
| 手段 | 特徴 |
|---|---|
| 年賀状 | フォーマルで伝統的だが減少傾向 |
| LINE | スピーディーで手軽、若い世代で主流 |
簡潔な挨拶が好まれる理由
長文のやり取りが敬遠される傾向が強まり、短くまとめた挨拶が好まれています。
LINEという特性上、スクロールせずに一目で読める文章が望まれます。
相手に負担をかけない「シンプルで誠実な言葉」がトレンドです。
| 避けたい文面 | 望ましい文面 |
|---|---|
| 事情説明が長すぎる文 | 一言で挨拶を控える旨を伝える文 |
| 形式的で堅すぎる文 | 丁寧ながら簡潔な文 |
個人情報やマナー面での意識変化
近年は個人情報保護の観点から、住所が必要な年賀状よりもLINEでのやり取りが安心と感じる人が増えています。
また、マナーに関しても「一律の形式」から「相手に合わせた柔軟な言葉づかい」へと変化しています。
形式にこだわるより、相手の気持ちに寄り添う挨拶が重視される傾向です。
| これまでの傾向 | 現在の傾向 |
|---|---|
| 決まりきった形式的な挨拶 | 相手に合わせて調整する挨拶 |
| 住所や郵送を伴うやり取り | スマホ一つで完結するデジタル挨拶 |
まとめ:喪中でも心のこもった挨拶をLINEで
ここまで、喪中のときにLINEで新年の挨拶を送る際のマナーや例文を紹介してきました。
最後に、大切なポイントを整理しておきましょう。
この記事で押さえておきたいポイント
喪中の挨拶で重要なのは「祝いを避ける」「丁寧さを保つ」「相手に配慮する」の3点です。
短くても誠実さが伝わる挨拶が最も大切です。
| ポイント | 具体的な行動 |
|---|---|
| 祝いを避ける | 「おめでとうございます」ではなく「本年もよろしくお願いします」と伝える |
| 丁寧さを保つ | 短文でも敬語を使い、感謝や気遣いを含める |
| 相手に配慮する | スタンプや絵文字を控え、落ち着いた文面にする |
例文を自分らしくアレンジするコツ
紹介した例文はあくまで参考です。
そのまま使うのも良いですが、相手との距離感や関係性に合わせて少し言葉を変えると、より気持ちが伝わります。
「自分らしい言葉」でまとめることで、形式的にならず心が届く挨拶になります。
喪中であっても、人と人とのつながりを大切にしたい気持ちは変わりません。
LINEという便利なツールを活用しつつ、心を込めて挨拶を届けましょう。

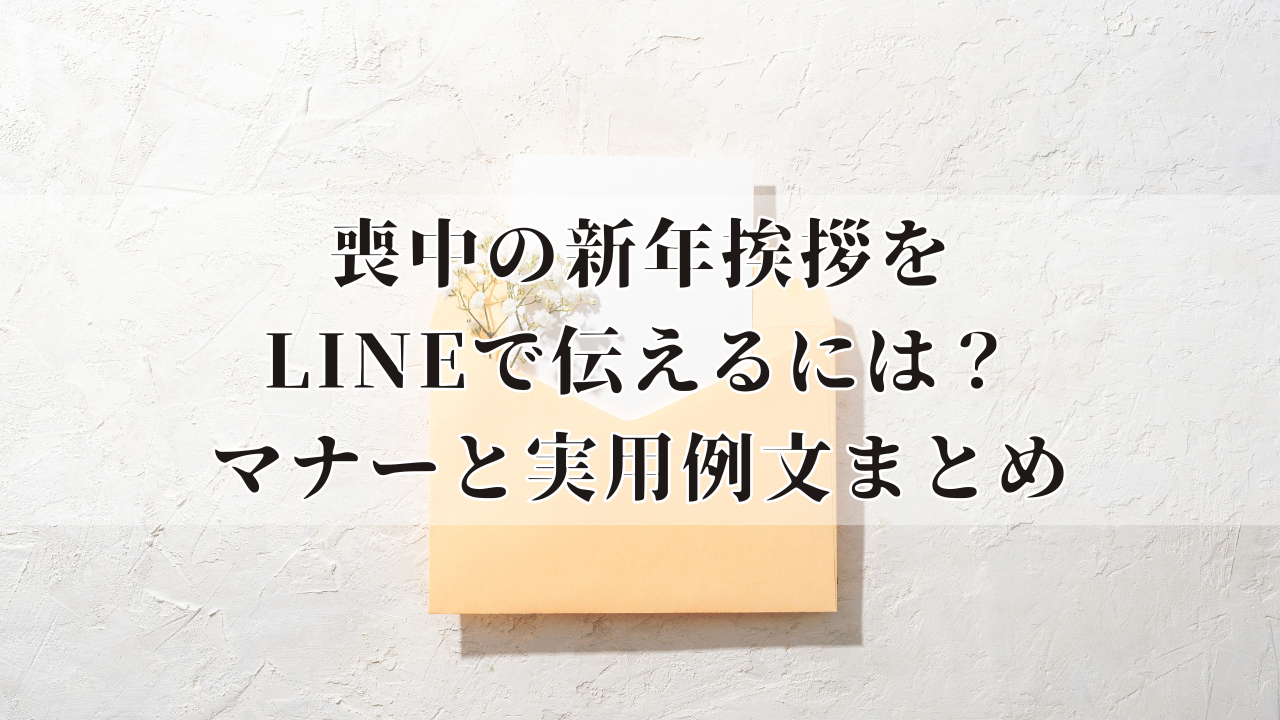
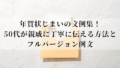
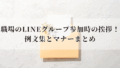
コメント